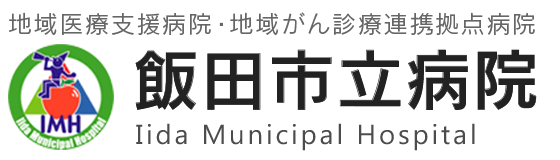がん遺伝子パネル検査
がんの遺伝子情報を詳しく調べることでより適した治療法を見つけ出します
- 遺伝子とがん
- がん発症の仕組み
- がんゲノム医療とは?
- がん遺伝子パネル検査とは?
- 対象となる方
- 検査の流れ
- よくある質問
- がん遺伝子パネル検査 対象患者さんのご紹介について(医療関係者の方へ)
- お問い合わせ
遺伝子とがん
私たちの体は約37兆個の細胞からできており、それぞれの細胞には「遺伝子」という設計図が組み込まれています。この遺伝子は、細胞の働きや増え方、寿命などをコントロールしている非常に重要な情報です。
「ゲノム」とは、遺伝子の全体像を指す言葉で、人間には約2万個の遺伝子があります。遺伝子に間違い(変異)が起こると、本来制御されているはずの細胞の分裂や修復がうまくいかず、がんになることがあります。
変異には、生まれつき持っている「生殖細胞系列変異」と、生活習慣や加齢、紫外線やタバコなどの影響で後から起こる「体細胞変異」の2種類があります。がんの多くは後者によるものです。
がん発症の仕組み
がんは、遺伝子の変異が蓄積されることにより発症します。通常、私たちの細胞にはDNAの間違いを修復する仕組みがありますが、何らかの理由でこの仕組みがうまく働かないと、異常な細胞が増殖して腫瘍になります。
がん細胞は無秩序に分裂し、まわりの組織に広がったり、血液やリンパの流れに乗って他の臓器に転移します。
がんゲノム医療とは?
がんゲノム医療とは、がんの原因となる遺伝子の異常(変異)を調べて、その情報をもとに一人ひとりに合った治療法を検討する医療です。従来の「がんの種類に基づく治療」ではなく、「遺伝子の異常に基づく治療」へとアプローチを変えることで、治療の選択肢を広げることができます。
日本ではこの医療を実施するために、国が「がんゲノム医療中核拠点病院」「がんゲノム医療拠点病院」「がんゲノム医療連携病院」を指定し、さらに、解析結果の収集・活用を担う「C-CAT(シーキャット)」という情報センターを設けています。全国の病院とC-CATが連携して、がんゲノム医療が提供されています。
当院は2025年4月1日に厚生労働大臣からがんゲノム医療連携病院として指定されました。
この医療の目的は、保険適用薬や治験薬を含めた治療の可能性を見つけることにあります。ただし、すべての方に有効な治療が見つかるわけではありません。
がん遺伝子パネル検査とは?
がん遺伝子パネル検査は、がんに関連する多数の遺伝子を一度に調べることができる検査です。がん細胞にどのような遺伝子の変異があるかを解析し、それに基づいて効果が期待できる治療薬や臨床試験の候補を見つけ出します。
この検査では、患者さんのがん組織や血液をもとに、数十から数百の遺伝子を一度に調べます。従来のように1つずつ遺伝子を調べるのではなく、「パネル(一覧)」として一括で解析できるのが特徴です。
現在、保険適用となっているがんゲノムプロファイリング検査
腫瘍組織を用いる検査
- OncoGuide™ NCCオンコパネルシステム
- FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル
- GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム
血液(血漿)を用いる検査
- FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル
- Guardant360 CDx がん遺伝子パネル
対象となる方
がんゲノム医療は、すべての患者さんが対象となるわけではなく、保険診療として受けられる条件が決められています。
- 標準治療が終了した、または標準治療の終了が見込まれる固形がんの患者さん
- 標準治療が確立されていないがん(原発不明がん、希少がん)の患者さん
これらの患者さんのうち、全身状態及や臓器機能等から、検査後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した方が対象となります。
また、検査に使用する組織検体や血液検体が適切に保存・採取されていることも条件のひとつです。
最終的に腫瘍内科担当医が検査の実施可否を判断します。
検査の流れ
1. 腫瘍内科受診のご案内
がんの進行や治療の状況に応じて、主治医ががんゲノム検査の必要性について説明し、腫瘍内科の外来受診をご案内します。
2. 検体の確認
過去に手術や生検などで採取された腫瘍組織が検査に適しているか確認を行います。保存状態や組織量が不十分な場合は改めて採取したり、採血を行う場合もあります。
3. 腫瘍内科担当医との相談・説明
がんゲノム医療の目的や検査の仕組み、得られる情報の限界、費用、家族への影響などについて、腫瘍内科担当医からご説明いたします。患者さんやご家族が納得したうえで、同意書に署名をいただき、検査費用の一部をお支払いいただきます。
4. 遺伝子検査
専門の検査機関に提出された検体は、数十~数百種類のがんに関連する遺伝子に異常がないかどうかを調べる解析を行います。検査の種類によって、解析に1か月~1か月半ほどかかります。
5. 検査結果の検討
遺伝子検査の結果をもとに、複数の専門家(臨床医、病理医、腫瘍内科医、遺伝カウンセラー、薬剤師、臨床検査技師、情報解析担当など)による専門家会議(エキスパートパネル)が信州大学医学部附属病院と共同で開催され、患者さんにとって適切な治療法や臨床試験の可能性について検討します。
6. 検査結果の説明
腫瘍内科担当医から検査結果のご説明をいたします。遺伝子異常や今後の治療に活用できる可能性などをお伝えします。残りの検査費用をお支払いいただきます。
7. 治療方針の検討
主治医と検査結果をもとに今後の治療方針についてご相談いただきます。必要に応じて、臨床試験への参加、薬剤の選択、再検査や遺伝カウンセリングなどの案内も行われます。
よくある質問
Q. 検査にはどれくらい費用がかかりますか?
A. 保険診療の場合、自己負担は検査申込時に132,000円、結果説明時に36,000円(3割負担の場合)です。高額療養費制度や限度額適応認定により実際の負担は数千円〜数万円となる場合があります。
なお、この金額は検査費用のみであり、別途、診察料などが必要となります。
Q. 検査結果の説明までどれくらいかかりますか?
A. およそ1か月半~2か月ほどかかることが一般的です。
Q. 検査で必ず治療薬が見つかりますか?
A. 2019年6月1日から2022年6月30日までに、全国で実施されたエキスパートパネル 30,822症例 のうち、約45%の方で治療薬の候補が示され、約10%の方が実際にその治療を受けています。
出典 国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/registration_status/
Q. 家族への影響はありますか?
A. 一部の患者さんでは生まれつきの体質(特定のがんにかかりやすいなど)に関連する遺伝子異常が見つかることがあります。この場合、ご家族(親、子、きょうだい等)も同様の体質がある可能性がありますので、ご希望により遺伝カウンセリングをご案内いたします。
Q. 検査を希望する場合はどうすればいいですか?
A. 現在当院で外来治療中の患者さんは主治医にご相談ください(入院中の方は検査を受けられません)。当院で治療を受けられていない患者さんは、現在通院中の医療機関の主治医の先生にご相談ください。
※患者さんからの直接の予約は受け付けておりません。
がん遺伝子パネル検査 対象患者さんのご紹介について(医療関係者の方へ)
患者さんをご紹介いただく場合には、地域医療連携係までお問合せください。
※患者さんからの直接の予約は受け付けておりません。
電話番号:0265-21-1257(地域医療連携係直通)
お問い合わせ
飯田市立病院 がん診療・緩和ケアセンター
住所:〒395-8502 長野県飯田市八幡町438番地
電話:0265-21-1255(平日 8:30~17:15)