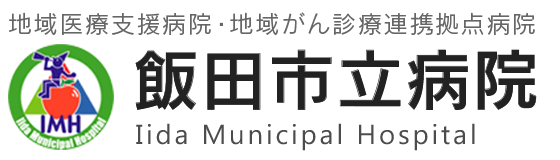1月
飯田市立病院 名誉院長
飯田市立高松診療所長
堀米 直人 医師
「上手な医療のかかり方」とは?
「上手な医療のかかり方」の1つ目は、身近な「かかりつけ医」を持つことです。
かかりつけ医は地域の医院・診療所・クリニックなど身近に居て、訴えをよく聞き病気の状態を判断し、自院で治療が可能である時は治療を行います。
しかし専門的で高度な医療が必要と判断した時は、紹介受診重点医療機関をはじめとする、設備とスタッフの揃った地域の病院などに紹介し、必要な検査や治療を早くスムーズに受けられるように調整します。
2つ目は2人主治医制。紹介先の病院で治療が終わり、安定した後のケアはかかりつけ医、定期検査や追加治療が必要な時は病院主治医が担当するという2人の主治医の役割分担で健康な暮らしを続けましょう。
3つ目。急な病気や体調不良の時はすぐにでも医療機関にかかりたいものです。
この頃は「救急医療がひっ迫していることからコンビニ受診は控えましょう。」とまで言われていますが、一刻を争う状態の時はためらわずに救急車を呼ぶのがよいと思います。
しかし、救急車を呼ぶか自分で受診するか迷ったり、かかりつけ医に相談する時間がない時は、飯田市休日夜間急患診療所をご利用いただくか
●大人の急な病気やケガは
長野県救急安心センター #7119
●子供の病気やケガの時は
子ども医療電話相談 #8000
に電話相談をしてアドバイスを受けることをお勧めします。
以上、身近で病気に関することを何でも相談できて、専門の医師・医療機関を紹介してくれる頼りになるかかりつけ医や電話相談は、上手な医療のかかり方のポイントです。
(参考)長野県医療政策課版 上手な医療のかかり方Book
2月
市立病院 形成外科 渡辺 勇太 医師
甘く見てはいけない 低温やけど
低温やけどをご存知ですか?その名称から、通常のやけどより軽いものだと思われる方もいるでしょうか。甘く見てはいけません。
低温やけどとは、低めの温度(44~50℃程度)に長時間(5分~6時間)さらされて起こるやけどのことです。44~50℃というのは短時間なら心地よく感じてしまう温度なので、初期はやけどを負っていることに気づきにくく、気づいたときには皮膚の深くまで損傷しているというケースが多いという、名前からは想像しにくい怖いやけどです。
しかし、その危険性を理解しておけば基本的に防げるものですので、まずはどんなところにリスクがあるのかを理解して予防に努めましょう。特に今の季節低温やけどを起こしやすいものとして、こたつ、湯たんぽ、電気毛布、カイロなどがあります。こたつに長時間入ったまま過ごさない、湯たんぽは就寝時には寝具から出す、電気毛布は電源を切ってから寝る、カイロは肌に直接触れないようにする、などの注意を怠ってはいけません。また、意外かもしれませんがスマートフォンやモバイルバッテリー、ノートパソコンなども原因となります。スマートフォン(特に充電中)を使用したまま寝たり、パソコンを膝などの上で長時間使用しないよう気をつけましょう。
はじめの症状は皮膚の赤みやヒリヒリ感など軽く見えても、時間の経過とともに皮膚がただれたり、壊死してくる場合があります。初期症状だけで重症度を判断することは非常に難しいものです。低温やけどかな?と思うような心当たりがあれば、その時点の症状の程度に関わらず、通常のやけどと同じくすぐに患部を流水で20分程度冷やしてから、すぐに病院を受診してください。
3月
市立病院 整形外科 林 幸治 医師
人生100年時代をどう生きる?
2025年1月現在、飯田市の65歳以上の老年人口比率(65歳以上)は35%(日本平均30%)です。更に高齢化に加え平均寿命も伸び、2025年現在、男性82歳、女性87歳です、これが100年時代といわれる由縁です。数字だけみれば万々歳で、自由にシニア世代(65歳以上の世代)を謳歌できると喜んでいいでしょうか。
皆さん、薄々気付いていると思いますが、この平均寿命の中には、寝たきりまたは介護が必要になっている期間が含まれます。ここで健康寿命(介護なく一人で生活できる年齢)があり、男性72歳、女性75歳です。この開き、男性10年、女性12年は自分一人では生きていけない期間となります。このある意味厳しい100年時代を皆さんはどう生き抜きますか。
寝たきり原因のトップは、整形疾患(骨折、転倒、関節疾患)で約23%に上ります。次は、脳血管障害(脳梗塞、出血)18.5%、認知症15.8%と続きます。
結論、100年時代を生き抜くには、寝たきりを防ぐ事、それは整形疾患を予防することが重要です。そのkeywordの1つが腰曲がりです。ご高齢になれば皆さん腰が曲がりますよね、これは普通の事なのでしょうか。いやいや、私はそうは思いません。腰曲がりは寝たきりへの警告信号、初めはちょっとした腰痛から、日々の悪い姿勢から、運動不足、更に骨粗鬆症も加わり圧迫骨折や脊柱管狭窄症発症によるものまで多岐にわたります。もちろん、加齢による原因も大きいですが、日々の生活で維持されているシニア世代も沢山おられます。
100年時代を生き抜くため、若い時から準備は始まっています。早期予防(適度な運動、骨粗鬆症の加療)から外科的治療まで微力ながら腰曲がり対策に協力させていただきます。
寝たきりを予防して人生100年時代を楽しく生き抜きましょう!!
4月
市立病院 小児科 伊藤 かおり 医師
川崎病ってどんな病気?
川崎病は、小児期(主に乳幼児期)のみに起こる病気です。急な発熱で始まることが多く、両方の目の充血、唇や舌が赤くなる、体の発疹(BCG痕が赤く腫れる)、手足が赤く腫れる、首のリンパ節が腫れる、という6つの主要な症状のうち5つ以上、または冠動脈病変が確認された場合や他の疾患が否定された場合に「川崎病」と診断されます。
冠動脈とは大動脈の付け根の近くから心臓を取り巻くように出ている血管で、心臓自身に血液を送ります。心臓が休みなく動き続けるために、なくてはならない血管です。川崎病で無治療の場合には3から4人に1人の割合でおよそ9から10日目以降から冠動脈病変を合併してしまうため、それを防止するために入院して治療を行います。治療をすればこのような心臓合併症を起こすことはほとんどなく、将来にわたって生活や運動の制限はありません。
近年少子化は言われていますが、川崎病の罹患率は年々増加を認めます。1970年以降2年ごとに川崎病全国調査が実施されており、この調査結果によると就学するまでには約50人に1人以上、つまり1から2クラスに1人以上は川崎病に罹患するということになります。
川崎病の原因はさまざまな説が論じられていますが、いまだ解明されていません。何らかの感染症が背景にあるという考え方が一般的で、それを裏付けるかのようにコロナ禍では感染予防策の徹底により感染症の流行自体が減少し、2020から2022年の川崎病患者数も一時的に減少がみられましたが、コロナ禍が明けてからは患者数がまた増加したことを日々の診療で感じております。
川崎病の症状は数日から10日かけてそろってくるため、最初の数日では診断できないことがよくあります。ご心配な点がありましたらまずはかかりつけ医にご相談ください。
5月
市立病院 皮膚科 上條 史尚 医師
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎とは、良くなったり悪くなったりをくり返す、かゆみのある湿疹を主な症状とする皮膚の病気です。湿疹とは、皮膚の表層に起こる炎症の総称で、皮膚炎とも呼ばれます。
アトピー性皮膚炎の原因は最近の研究で、「皮膚バリア機能異常」と、免疫の異常によって起こる「アレルギー炎症」「かゆみ」の3つの要素が互いに関連しながら発症することがわかってきました。そのため、治療も三位一体で考えていくことが重要となってきました。
アトピー性皮膚炎の治療の基本は症状に応じて「薬での治療」「スキンケア」「悪化させる原因の対策」の3つを組み合わせた治療です。
最終目標は、あまり薬を使用することなく日常生活を送れるようになることです。
一般的に、アトピー性皮膚炎の治療では、ステロイド外用薬で炎症を抑え、保湿外用剤で皮膚のバリア機能の低下を防ぐという組み合わせが基本となり、補助療法として抗ヒスタミン薬(一般的なかゆみ止め内服薬)が使用されています。
ほとんどの方はこれでコントロールできるのですが、一部の中等症から重症の患者さんの中には、このような従来の薬では症状がなかなかコントロールできない方がいらっしゃいます。
そのような患者さんの新しい選択肢として、近年、注射薬などこれまでとは異なる作用機序をもつ新しいタイプの薬が続々と登場しています。ただし、使用できる基準があり、高額な薬剤でもあります。
今まで受けている治療で十分な効果が得られない、毎日かゆくてつらいという患者さんは、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。
6月
市立病院 泌尿器科 中藤 亮 医師
前立腺肥大症
前立腺は男性に特有の臓器で精液の主な成分である前立腺液を分泌します。前立腺は膀胱の出口の部分で尿道を取り巻くようにあり、加齢に伴って大きくなります。尿道を圧迫するようになると尿の通り道が狭くなり、排尿の症状を引き起こします。これが前立腺肥大症です。
代表的な症状として、尿の勢いが悪くなり出るのに時間がかかるようになります。排尿しても膀胱に尿が残るようになり(残尿)、進行すると膀胱がいっぱいでも尿が出せない状態(尿閉)になります。尿閉が長期に続くと腎臓の機能が低下してしまい生命にかかわる事態にもなります。
前立腺肥大症の治療として、まずは薬物療法があります。排尿の時に前立腺の部分の筋肉を緩めて尿が勢いよく出るようにするお薬や、男性ホルモンの働きを抑えて前立腺を大きくしないようにするお薬、漢方薬などがあります。
残尿が多い場合や、尿が出なくなってカテーテル(排尿のための管)が必要な場合は手術治療を行うこともあります。手術は前立腺がある程度以上の大きさで、膀胱の機能が保たれている人が対象になります。標準的な手術方法として尿道から細い内視鏡を入れて前立腺を少しずつ切り出す前立腺切除術があります。出血や手術時間などの負担があり、心臓や肺の機能などに問題のある方はできません。体の負担が少ない手術方法として、前立腺に水蒸気を注入して小さくさせる前立腺水蒸気治療があり、昨年から飯田市立病院でも行えるようになりました。尿道の広がり具合は切除する手術よりも小さくなりますが、手術時間や出血量を大幅に少なくすることができます。
7月
市立病院 産婦人科 池田 枝里 医師
出生前診断
出生前診断、出生前遺伝学的検査は、産科医療から切り離すことができないものです。
染色体疾患を含め、赤ちゃんが何らかの先天性疾患をもって産まれてくることは、誰にでも起こりえます。生まれつきの変化とは、多様性であり、個性の一部ですが、人とは違った特徴をもつことで生きづらさにつながる可能性は否定できません。
妊娠の継続や中断については、ご本人、ご家族の選択が尊重されるべきです。産科医には正しい情報を伝え、一緒に向き合い考えることが求められていると思います。
飯田市立病院産科は、日本医学会の出生前検査認証制度運営委員会より、2023年10月1日付けでNIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)を実施する連携施設(基幹施設:信州大学医学部附属病院)として認証されました。同時期に、出生前診断をご希望される妊産婦さんとパートナーにカウンセリングを受けていただく“いぶき外来”を開設しました。
無事出産されてからも、自ら命をたつ方もいます。日本産婦人科の母体安全への提言2023では、自殺は、頭蓋内出血・梗塞に次いで、妊産婦死亡の原因の第2位となっています。2020年から2022年の妊産婦の自殺報告数は過去最多であり、産後の報告が増加しています。妊娠・出産はあくまでスタートであり、出産後の長期的なサポートが必要であると日々感じています。
妊娠・出産はスタートであり、これからの家族のあり方、今後どのように過ごしていかれたいか、一緒に共有するための外来となっています。
出生前診断を含めて、出生前にご家族で思いを共有することは、それぞれが歩んでいく道のきっかけとなるものと考えています。
8月
市立病院 眼科 森 俊男 医師
緑内障治療の現状と低侵襲手術(MIGS)について
緑内障は、40歳以上の日本人の約20人に1人がかかるとされる身近な目の病気です。眼圧の上昇などにより、目の奥にある視神経が徐々に傷んでいき、見える範囲(視野)が少しずつ狭くなっていきます。加齢とともに発症率は高くなり、特に強い近視のある方は注意が必要です。一度失った視野は回復しないため、緑内障は日本における失明原因の第1位となっています。
この病気は初期には自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行してしまうため、早期発見・早期治療がとても重要です。緑内障の治療は目薬から始まりますが、種類も多く、必要な本数をきちんと点眼できない方が少なくありません。目薬の効果が感じにくいことや副作用もあって中断してしまい、結果として病気が進行してしまうケースが多いことが問題となっています。こうした背景から、近年では目薬を増やすよりも、早めにレーザー治療や手術を検討する方針が広がっています。
最近注目されているのが「低侵襲緑内障手術(MIGS)」です。従来の手術に比べて目の負担が少なく、安全性も高いのが特徴です。かつての緑内障手術は1時間ほどかかっていましたが、MIGSの手術時間は5~10分程度と短く、白内障手術と同時に行うことも可能です。適切なタイミングで手術を行うことで、点眼薬の数を減らし、患者さんの負担を軽減できるメリットもあります。
毎年3月上旬には「世界緑内障週間」に合わせて、公共施設や病院などが緑にライトアップされ、緑内障の啓発活動が行われています。当院もこの活動に参加しています。40歳を過ぎたら、ぜひ定期的な眼科検診を受けて、大切な目の機能を守りましょう。
9月
市立病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 市瀬 彩 医師
耳鳴りについて
煩わしい耳鳴りに悩まされていませんか?
現代の医学では、残念ながら耳鳴りを根本的に消す方法はありません。しかし、耳鳴りのメカニズムを知り、気にならない・気にしない工夫をする事で、症状を緩和することができます。
耳鳴り患者さんの9割に難聴がありますが、これは耳鳴りが音を聞く仕組みと強い関係があるためです。耳に入った音は、鼓膜から内耳の蝸牛という音を感知する器官に伝えられた後、聴神経を通り脳へ伝達されます。蝸牛などに異常が生じて難聴になると、脳に伝わる音が弱くなります。すると届かなくなった音を探そうと脳が過剰に反応して、耳鳴りが生じると考えられています。耳鳴りは脳が音を作り出してしまっている状態と言えます。また、不安やうつ状態、不眠などのストレスは、脳内で耳鳴りと刺激し合い、耳鳴りを悪化させる原因になります。
このような仕組みから、難聴のある患者さんでは補聴器で耳に入る音を増やすのが有効な治療法です。音の少ない環境では耳鳴りを感じやすいため、音楽をかける・川の音などの自然音を流すといった、静かになりすぎない工夫も必要です。耳鳴りに注意を向けて苦痛を感じると、耳鳴りが悪化する悪循環に陥るため、耳鳴りを探さない心掛けも大切です。また、ストレスへの対応も重要であり、睡眠薬・抗うつ薬が必要な場合など、症状によっては精神科や心療内科への受診をお勧めすることもあります。
なお、突発性難聴などの治療が必要な病気が原因の耳鳴りもあるため、急な耳鳴りや難聴といった症状がある場合は、早めにお近くの耳鼻科へご相談ください。
10月
市立病院 放射線治療科 伊奈 廣信 医師
定位放射線治療について
がんの治療というと手術、抗がん剤、放射線治療などが挙げられます。手術や抗がん剤は一般的にも認知度が高いと思われます。さて、放射線治療のイメージは浮かぶでしょうか?ちなみに何年か前にドラマ化された「ラジエーションハウス」は放射線治療ではなく、放射線診断のお話です。医学生に一般的な放射線治療で使う線種を聞いても正解の方が少ないほど印象が薄いのが実情です(正解はレントゲンやCTと同じX線です)。
さて、そんな放射線治療ですが、治療を始めたら平日は毎日行います。1~2カ月毎日です。仕事をされている方や遠方の方は特に大変ですが、皆様頑張って通っていただいています。なぜ1~2カ月も行うかと言いますと1回当たりの放射線量を減らして治療回数を増やした方が副作用を少なくできるからです。
そんな放射線治療の中に定位放射線治療という少し特殊な治療があります。いわゆる「ピンポイント治療」というもので、治療範囲を絞ってそこに1回当たり大線量を当てます。治療期間は1~2週間と通常より短いです。しかも通常の1~2カ月の放射線治療よりも治療効果が高いです。当院でも数年前から定位放射線治療を行っています。誰にでも適応があるわけではありませんが、適応がある場合は行うことが多いですので、放射線治療科で上記の様な説明を受けたら、“これか!”と思っていただけると何よりです。
そもそも放射線治療とは縁がない方が良いかもしれませんが、いざというときはよろしくお願いします。
11月
市立病院 外科 福留 惟行 医師
手術支援ロボット「hinotori (ヒノトリ)」が飯田市立病院にやってきます
飯田市立病院では、市民の皆さんが安心して受けられる、体への負担が少ない医療を目指して、手術支援ロボット「hinotori(ヒノトリ)」を導入します。
でも「ロボットで手術って、ちょっと怖いかも…?」といった疑問をお持ちの方も多いと思います。
そこで、みなさんにわかりやすく知っていただけるよう、Q&A形式でご紹介します。
Q 「手術支援ロボット」って何ですか?
A:手術支援ロボットは、医師が操作して使う「手術のアシスタント」です。
人の手では難しい細かな動きも、ロボットアームを使うことで正確に行えるようになります。あくまでも、医師が操縦する機械で、自動で勝手に手術をするわけではありません。
Q 「hinotori(ヒノトリ)」はどんなロボットですか?
A:「hinotori(ヒノトリ)」は、外科医の手術をサポートするために開発された国産の手術支援ロボットです。
術者は4K画質の3Dモニターを見て細かな血管などを確認しながら、人の手の関節可動域を超えた動きができるロボットアームを操作して手術を行うことで、緻密で出血を抑えた手術にも役立ちます。
Q ロボットで手術すると何が良いの?
A:ロボットを使うことで、小さな傷で手術ができるため、体への負担が軽くなります。例えば胃の手術において、開腹手術では傷はみぞおちからへそ下までとなりますが、ロボット手術では約1cmの傷が6カ所程度で手術可能です。その結果、痛みの軽減や回復の早期化が期待でき、入院期間の短縮や早期の社会復帰につながる場合もあります。
Q どんな病気に使われるのですか?
A:全国的にはすでに消化器外科(胃、大腸、食道など)、呼吸器外科(肺)、泌尿器科(前立腺、腎臓)、婦人科(子宮、卵巣)などの幅広い分野においてロボット手術が実施されています。
市立病院ではまず消化器外科分野のがん手術で使われる予定です。
将来的には泌尿器科や婦人科、呼吸器外科など、他の診療科での活用も予定しています。
Q 飯田市立病院ではいつからロボット手術が受けられるの?
A:飯田市立病院では令和7年9月に導入し、手術に携わるスタッフのトレーニングなどの準備期間を経て、令和7年度冬季からロボット手術が本格的にスタートします。
Q ロボットに手術されるのは少し怖いです…
A:ロボット手術は認定資格を取得し、十分なトレーニングを積んだ医師によって行われます。ロボットはあくまで医師の「手の代わり」をするだけで、ロボットが勝手に動き出すことはありませんのでご安心ください。ロボット手術を希望しない場合は従来の手法による手術も可能ですので、主治医にご相談ください。
Q ロボット手術を選択すると費用は高くなりますか?
A:一部の手術では若干高くなるものがありますが、保険適用となりますので費用負担は従来とほとんど変わりません。入院期間は短くなることが多いので、結果として費用負担が軽くなる場合もあります。費用や手術内容については、主治医または病院スタッフが詳しくご説明しますので、お気軽にご相談ください。
飯田市立病院は「hinotori(ヒノトリ)」を活用し、安心で負担の少ない医療を市民のみなさんに提供してまいります。 これからも、市民のみなさんが安心して暮らせる地域医療を守り、より良い医療環境づくりに努めてまいります。
12月
市立病院 麻酔科 岩澤 健 医師
全身麻酔と口腔内管理
全身麻酔下での手術では、口から気管に気管チューブを挿入します。口腔内には1gの歯垢に1億という非常に多くの細菌がおり、気管チューブを挿入するのに伴い、口腔内の細菌を肺に押し込めてしまうことで肺炎や気管支炎といった危険が生じます。また、動揺している歯(グラグラしている歯)がチューブなどに当たり、歯を飲み込んでしまったり、歯が気管内に入ってしまう可能性があります。
近年の研究では手術前からの歯科による口腔管理が、術後の肺炎発症予防に繋がることが示されています。さらに、口腔内や頭頸部領域、食道のがんなどの手術後は、それらの手術部位の感染症を発症する危険があります。
これらの危険を予防するために、手術などの治療を受ける患者さんを対象に、歯科医師や歯科衛生士が、入院前から退院後まで一貫して口腔内の状態の管理を行う場合があります。これは、全身の治療を安全かつ効果的に進めるため、また術後の合併症を予防し、患者さんの回復を促すために非常に重要とされています。
当院では手術が決まった後に、歯科口腔外科への紹介後に口腔内の診察、むし歯や歯周病などの歯科治療、歯みがき指導や歯石除去、義歯清掃、口腔粘膜炎の予防・治療などが行われます。これらのケアは、病院内の歯科だけでなく、かかりつけの一般歯科医院でも受けることが可能ですので、がん等の全身疾患の有無に関わらず、健康な時から、かかりつけ歯科に定期的に通い、良好な口腔衛生状態、および歯周組織の維持をおこなっていただきたいです。